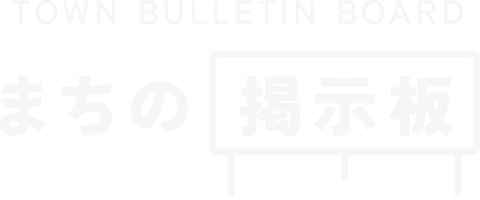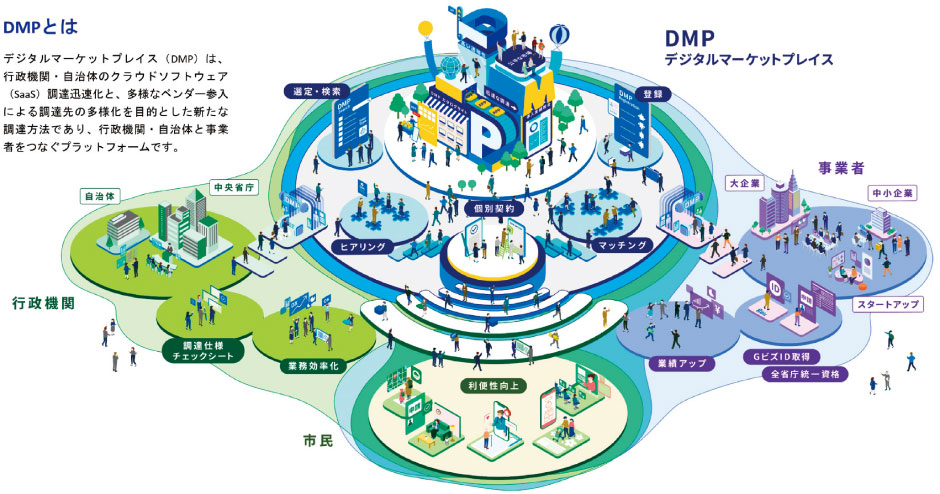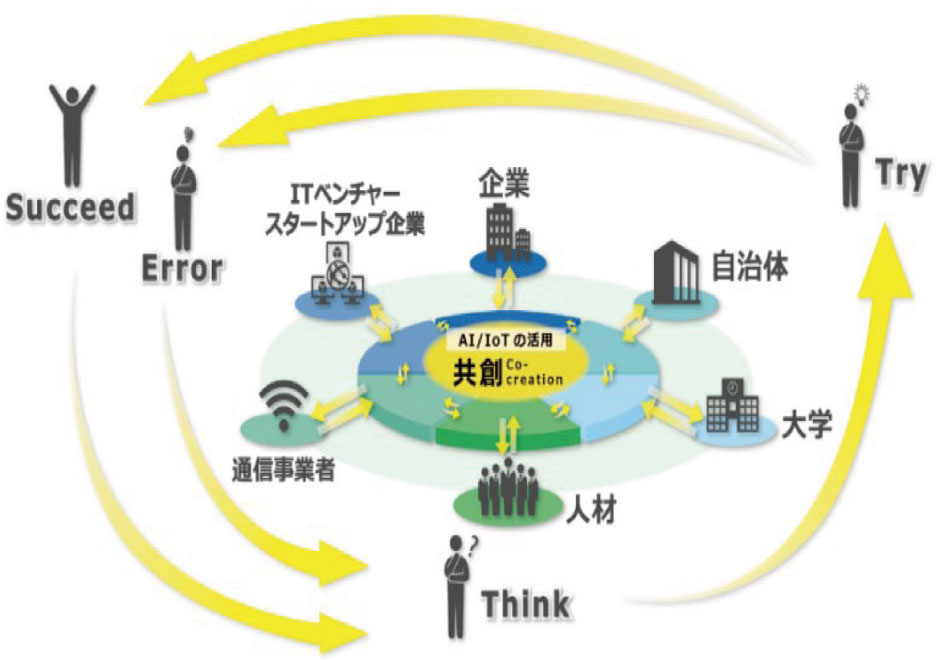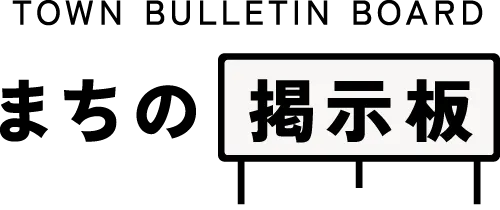「フェアで持続可能な移住促進」をテーマに、地域政策や情報発信に関する研究・提言を行っている、国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)の伊藤将人氏。競争や流行にとらわれず、本当に必要なメッセージを届けるために必要なことは何か? 各地の自治体との協働や調査を通じて見えてきた、移住施策、シティプロモーションの本質について話を聞いた。
著者プロフィール

伊藤 将人
伊藤 将人
社会学者(博士)。長野県出身。
国際大学グローバル・コミュニケーション・センター研究員・講師。
長野大学環境ツーリズム学部卒業、一橋大学大学院修了後、地方移住や関係人口、観光など地域を超える人の移動に関する研究や、持続可能なまちづくりのための研究・実践に長年携わる。
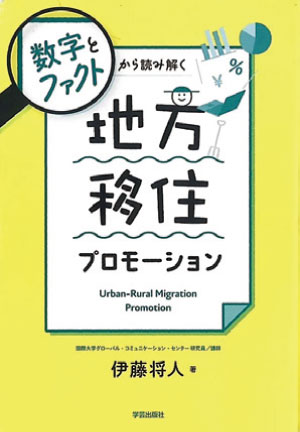 著書に『数字とファクトから読み解く 地方移住プロモーション』『移動と階級』など。
著書に『数字とファクトから読み解く 地方移住プロモーション』『移動と階級』など。
POINT!
「ない」より「ある」を見つける ~ 当たり前を見直すことが大切
地方自治体の方との会話でよく聞かれるのが、「うちの町には何もない」という言葉です。しかし、私は別の視点を提案します。実は小さなものでも、自分たちの地域に“これがある”という棚卸しをし、小さくてもいいから発信することがとても大切だと思っています。
例えば、私が生まれ育った長野県池田町では、ハーブを活用したまちづくりを進めています。規模は北海道などの有名な地域には及ばないものの、地道に数十年かけて取り組んできました。地元の人々は「他と比べると全然だよね」と感じていても、日本全体の視点で見れば「ハーブに興味のある層」にとっては、十分に魅力的な場所になり得ます。
「地域が持っているものの価値を判断するのは、自分たちではなく外の人たちである」という認識が重要です。地域資源を時代に合わせてブラッシュアップし、活用していくことこそが、移住促進やシティプロモーションの本質であると、私は考えています。
POINT!
2030年には関係人口ブームは終わる!? ~ 誰のためのものかを明確に
地域政策に関しては、これまでも1970年代の「Uターン、Jターン」、1990年代の「Iターン、UIJターン、交流人口」、2000年代の「二地域居住者、交流居住」など、時代によって新たな“人口”の定義をつくり、期待し、関心が薄れる、ということを繰り返してきました。歴史的に考えると2030年代には新しい概念が生まれる可能性もあります。
「関係人口」は観光や移住、定住など多くの問題の解決策として期待されていますが、万能薬ではありません。まず大切なのは「何のための関係人口なのか」という本質的な問いです。単に「役に立つ人に来てほしい」という視点では、「じゃあ私は違うのか」と疎外感を覚える人も出てきます。地域に関わる人を増やしたいのか? 地方創生なのか、都市の人びとのふるさとの創出なのか? など、現在の政策と照らし合わせて自分たちなりに定義することが、重要になってきます。
POINT!
取り合いではなく助け合い ~ 広域連携で選ばれる町に
シティプロモーションや移住促進において、広域での自治体連携は非常に重要です。例えば、ある人が◯◯市への移住を検討していても、実際に訪れてみると「違う」と感じることがあります。そんなとき、「あなたの条件だったら隣の自治体がいいかも」と紹介できる関係があれば、地域全体として「希望を実現できる」体制ができます。
実際の移住検討者は自治体の境界をあまり意識せず、生活圏として捉えています。例えば、長野県池田町では大きな書店がなくても、車で40分の松本市に大型書店があることが移住の決め手になったという方に会ったことがあります。
これは観光についても同じで、移動が負担にならない範囲は一つのエリアとして考え相互に補完し合い、地域全体の魅力を高められます。「ないものはない」ではなく「広域で見ればある」という発想の転換が重要だと思います。
POINT!
シティプロモーションは恋愛と同じ ~ 好きになってもらうには相手を知ること
シティプロモーションや移住促進は、恋愛と似ています。
「好きになってほしい」と願うだけではなく、まず相手の気持ちを知る努力が必要です。
成功している自治体には共通点があります。自ら収集分析したり、自身が移住者の立場になって行動していることです。たとえば、移住者に対して「どんなメディアで最初に地域を知りましたか?」「その後、どんな情報を得ましたか?」といったアンケートを実施することで、効果的な情報発信の手がかりが見えてきます。
調査では、20代以下ではInstagramが圧倒的な情報源となっている一方、60代以上には自治体のパンフレットや雑誌が効果的であることがわかっています。ターゲット層に応じて、使うべきメディアは大きく異なります。広く浅くではなく狙った伝えたい人たちにしっかり刺さるメッセージ、発信方法を選ぶ。それが地域のファンを増やし、継続的な関係へとつながっていくと考えています。