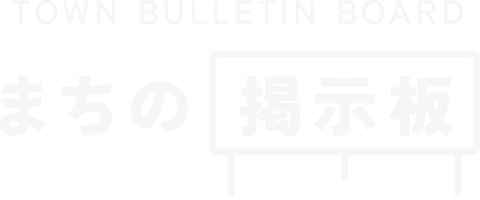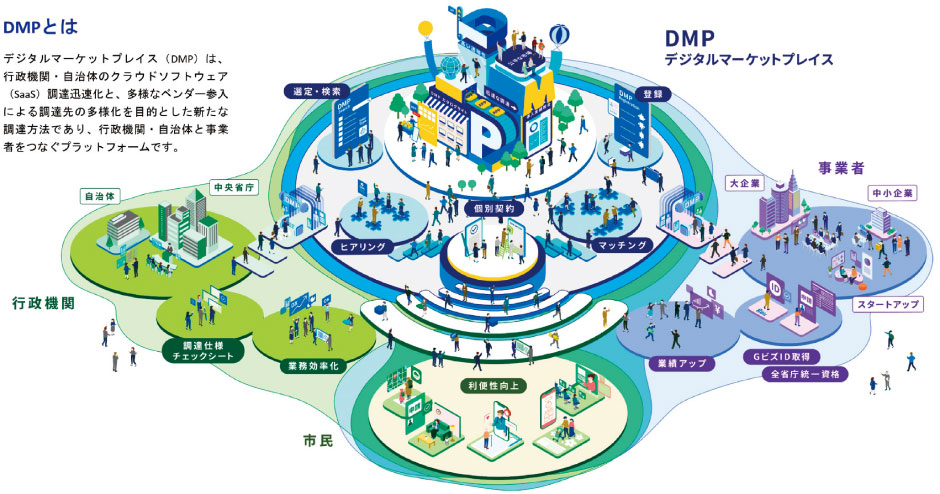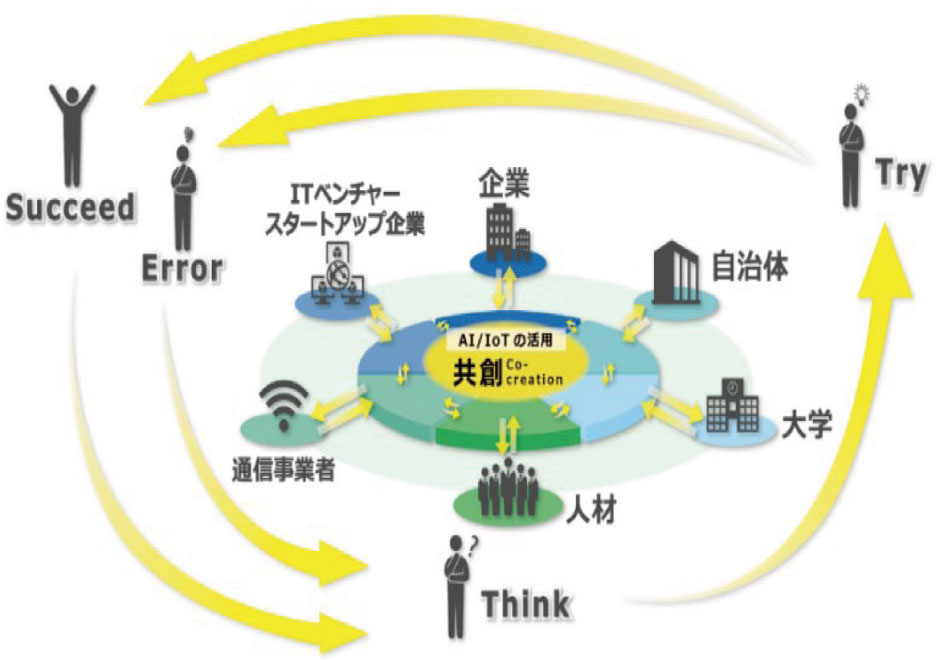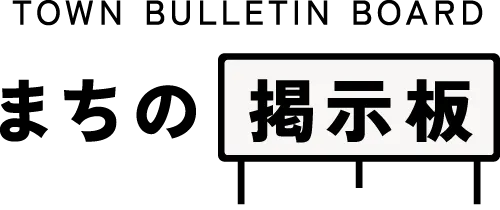人口1,000人の昭和村が実現した
「住民と向き合う」ための庁内DX革命
「役場の職員のことがわからない」─。住民からの声が、福島県昭和村の業務改革の出発点だった。人口約1,000人、職員数も限られる小規模自治体。一人の職員が複数の業務を抱える中、いかに住民と向き合う時間を生み出すか。
この課題に対し、昭和村はローコード・ノーコードツールを活用した独自のアプローチで答えを出した。専門業者に頼らず、職員自らがアプリを開発。小さく始めた取り組みが、今では294個のアプリが稼働する全庁的なDXへと発展している。

福島県昭和村 総務課 企画創生係長
小林 勇介
平成22年入庁。広報、農業、観光部門を経て総務課へ。企画部門での経験が長く、第6次昭和村振興計画の策定にも携わる。令和3年よりDX推進チームのサブリーダー、現在はリーダーとして、ローコード・ノーコードツールを活用した業務改革を推進。「先端的過疎への挑戦」を掲げ、小規模自治体のDXモデルを構築している。
DXで業務改革を起こし、住民と向き合う時間を作る
DX推進に取り組まれたきっかけを教えてください。
「第6次昭和村振興計画」にDX推進の方針を示して、令和3年からDX推進チームを発足しました。その背景としては、世の中のトレンドということもありましたし、昭和村は住民も少ないんですが、職員もやっぱり少なくてー。一人の職員がいろんな業務を兼務しているような状況だったんです。今後ますます人口が減っていっても、行政としてやるべき仕事は多分変わらないし、逆に業務は増えていくかもしれない。そんな中で、住民の皆さんからよく聞かれているのが、「役場の職員のことがわからない」という声でした。外から入ってきた職員もいるので、そう感じる住民がいるのは無理もないことなんですが…。
とはいえ村に住んでいるのは住民なので、地域の課題を解決していくにあたっては、住民が何に困っているのかを知らないと始まらない。そういうところに充てる時間を作るために、まずは我々の業務を効率化しなければならないな、と思ったんです。
その手段として、なぜローコード・ノーコードツールを選ばれたのでしょうか。
実は当時の私はkintoneを全く使ったことがなくて、文書決裁の専用システムを入れるつもりだったんですよ。しかし、トライアルを重ねていくうちに「これは単に文書決裁だけのシステムではなく、考え方次第で色々な用途に使えるのではないか」と気づいたんです。文書決裁専用のシステムは一つの用途にしか使えないのに、それなりのお金がかかる。その点、ローコード・ノーコードツールなら汎用的に使えますし、何よりシステムを作るという作業にあたって、専門の業者に委託しなくても職員で対応できる。これが一番大きかったですね。
手集計から自動化へ、小さな成功体験の積み重ね
最初はどのような業務から始められたのですか。
超過勤務の申請ですね。当時はコロナのワクチン接種業務もあったので、それも早めに対応しました。超過勤務の申請は、ローコード・ノーコードツールの導入前までは、各係から紙で出てきていたものを、全て給与担当が手集計していました。職員がエクセルで作って、印刷して、ハンコを押されて出てきたのを集計するという作業です。給与担当は、支払いの直前になると毎回残業しているような状態。
それがデータで来れば、CSVで吐いて計算するだけでいいので、かなり楽になるんじゃないかな、と。当時の給与担当者からも「大変だ」という声が挙がっていたので、そこから始めました。
その後、どのように全庁展開されていったのですか。
最初はDX推進チームの中で「小規模からトライアンドエラーをしていこう」という方針だったんですが、課長が非常に前向きで、「だったらもう全体でやろうよ」という雰囲気になったんです。昭和村には本庁舎と三箇所の出先があって、紙で決裁を回すと書類がどこにあるのかわからなくなったりすることがありました。それに、紙では一人ずつしか見ることができないんですよね。
でも電子決裁なら、作業者を複数に設定しておけば同時に閲覧できますし、そもそも物理的な書類を持って行き来するという行為自体がなくなります。また、村長や各所属長が出張していても、スマートフォンでポチポチ決裁ができる。個人の端末からでも安全に利用できる仕組みとルールを作ったので、全職員に専用の端末を配る必要もありませんでした。

職員が見る「お知らせ画面」には、決裁中の起案や回覧状況が表示され、現在どのようなタスクが進行中なのかが一目でわかる
現場の課題から生まれる、本当に必要なシステム
導入当初、アプリ制作の伴走支援などは受けられたのですか。
いえ、最初から全て私のほうで作っていました。もともとホームページを作ったりするのは得意で、ある程度JavaScriptなどは書けていましたし、そもそも最初のうちはそれほど高度なことをしていなかったので。ネットのエンジニア系の記事や、サイボウズの開発者向けのコミュニティなどを参考にしながら作っていきました。実際のところ、行政の仕事は行政にしかわからないところもあるじゃないですか。伴走支援を入れたり外注に出したりしても、要件定義ができる人材がいないと、最終的に欲しかったものと違うものができてしまうこともある。だったら自分たちでがむしゃらにやった方が、結果として時間もエラーも少なくて済むかな、と。自分で対応できる部分から小さく始めて、もし外注や支援が必要になったら後から検討すればいいと判断しました。
現在kintoneで運用されているアプリは294個あります。できるだけ簡単に、紙のときと見た目は違ってもフローは同じにするということと、なるべく自動化していくことを意識していますね。できるだけハレーションが起きないように、ワンクリックの手間を少しでも減らせるように作っています。
給与関係や電子決裁の他には、どのような分野で活用されていますか。
本当に多岐にわたりますね。例えば農業部門では、有害鳥獣対策用品の貸し出し管理のアプリを作りました。エクセルで管理していたり、そもそも管理できていなかったりして、在庫があるのかないのかさえわからない状態だったのが、改善されたと思います。
他の自治体で絶対やっていなさそうなところでいうと、防災行政無線の管理です。それまでは放送する内容を書いて紙で出力して、課長の決裁をもらってから放送していたのですが、今はこのプロセスにもローコード・ノーコードツールをフル活用しています。kintone上で音声合成まで行って、Chromeの拡張機能を使って、防災無線のシステムにワンクリックで転記できるようにしたんです。紙で決裁をもらった後に、無線室に足を運んで専用の端末を操作するという作業が、今では数クリックでできるようになりました。
住民申請にもローコード・ノーコードツールを活用されているそうですね。
マイナンバーとも連携して、申請を受け付けられるようになっています。ただ、小さい自治体ではよくあることだと思うんですが、オンライン申請の利用者が多いというわけではないんです。でも、紙で来た申請を職員が入力すれば、皆がリアルタイムで同じ情報を見られるので、非常に便利になりました。

複数のアプリが見やすく整理され、さらに業務効率をアップ。カラフルなアイコンも特徴的
業務改革の効果で、新しい働き方も実現
職員の方々のスキルやリテラシー向上の取組は?
いえ、特にこれといった取組はしていないんですよ。アプリの制作も、今もまだ主に私の方で行っています。最近はDXチームのメンバーの一部も作ってくれるようになった段階ですね。原課の職員が迷って考えながらアプリを作ることも大事ですが、まずはそこの時間を無駄にしないで、皆には効果を体感して欲しいんです。それで時間のゆとりができた後に、挑戦してくれる人が出てきたらいいかな、と思っています。
皆さんの働き方に変化はありましたか。
職員一人ひとりに、以前よりもゆとりが出てきたことを実感しています。余剰時間ができて、住民と対話する時間が生まれているんです。私たちの仕事は「住民ありき」だという考えは一貫しているので、思い描いた姿に少しずつ近づいているように思えて、手ごたえを感じています。
昭和村には今、リモートワークの制度があります。一昨年前にリモートワーク制度が作られたんです。この制度ができたことで、介護休暇や育児休暇中であったり、お子さんや家族の体調不良でお休みを取ったりと、いろんな事情で出勤できないときにも皆が安心して働けるようになったと思います。自宅にいてもチャットツールで連絡が取れますし、クラウド上で決裁も回せますからね。
また、今までは庁舎内にサーバーを置いていたものを全てクラウドに移行したことで、災害時のリスクヘッジにもなっていると思います。
万が一大きな災害が起きても、スターリンクでも何でもインターネット環境さえ作れれば、業務を継続できる。昭和村は東日本大震災を経験していますが、もしまた同クラスの地震が起きたときに、庁舎が無事かどうかわかりません。その意味でも、データをクラウドに退避しておく意義は大きいと思います。

申請や決裁がオンラインで完結するようになり、働き方や村の行政そのものにも変化の兆しが見えている
村のポテンシャルを信じて、住民サービスの未来を描く
今後の展望について教えてください。
高齢者のデジタルデバイド対策として、昭和村では無料でタブレットを配っているんですが、それをもっと日常的に使ってもらえるようにしたいです。例えば、朝起きたら「今日は元気です」「少し体調が悪いです」みたいな安否確認ができないかな、と。専用のシステムを入れるという方法もあるんですが、ここにもローコード・ノーコードツールを活用したほうが、何かあった時に専用のシステムにログインすることなく、行政側がすぐに「おかしいな」と気づけると思うんです。
あと、去年の秋口からは「デジタルなんでも相談室」を設置しました。行政に関することだけではなく、「パソコンが起動しなくなった」「迷惑LINEをブロックしたい」とか、本当に多種多様な相談を受け付けています。困った時に教えてくれる人がいないと、そこで止まっちゃうんですよね。なので、リアルタイムですぐに相談できる体制を作ることで、住民の皆さんがデジタル嫌いにならないようできればと思っています。

2027年に100周年を迎える福島県昭和村。昔も今も変わらない「より良い村になってほしい」という願いを胸に、「挑戦する心」を持ち続ける
最後に他の自治体へのメッセージをお願いします。
多分、自治体でローコード・ノーコードツールを活用したいと考えたときに、最初にぶち当たる壁はLGWANの問題です。費用的にも高いですけれども、そのコストを跳ね返すぐらいの効果は必ずあると思います。本当に様々な用途に使えるので、個別のシステムをいくつも入れるよりは、トータルコストを抑えられますしね。「できる・できない」の前に「やるか・やらないか」だと私は考えているので、強い信念を持って、最終的に「こうしたい」というビジョンや思いを持っていけば、必ず理解してくれる人もいると思います。
「第6次昭和村振興計画」では、「100年後も 昭和村が 昭和村であるために始める これから10年のこと」というスローガンを掲げています。一般的に「過疎」という言葉にはマイナスなイメージがありますけれども、逆に言えば、日本も人口減少社会に入って、昭和村で起きていることが今後は全国で起きてくるわけです。だったらもう、先んじて我々がいろいろ挑戦していこうよ、と。「先端的過疎への挑戦」という反骨精神で、やっていきたいと思います。
(取材日:2025年6月3日)
福島県昭和村 総務課 企画創生係
〒968-0103 福島県大沼郡昭和村下中津川字中島652
TEL:0241-42-7717(直通)